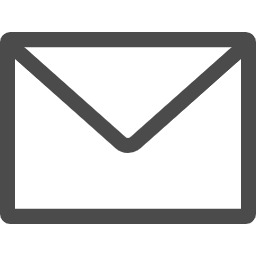監理措置制度とは
監理措置制度は、日本からの国外退去に該当するような疑いのある人、または国外退去が決定された人たちを、監理人という人が見守りながら、決まった期間のあいだ社会の中で普通の生活を続けられるようにして、収容施設に閉じ込めることなく、日本から出国してもらう手続きを進める仕組みです。
一時的に収用を解除する手段としては「仮放免」の制度が活用されていました。令和5年の改正入管法(施行は令和6年6月10日)によって監理措置制度が創設され、収容しないで手続きを進める手段の基本はこの制度によって行われる事となりました。
ただし「仮放免」の制度そのものは廃止されてはおらず、監理措置制度が適当ではない人道上や健康上の理由があるときなどに活用される仕組みになっています。

初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください。
監理措置制度の対象になる人
この制度の対象者は、退去強制令書が発付される前か発布された後の人のどちらかです。
言い換えると、一般的に国外強制退去と言われる退去強制処分にあてはまる疑いがあって審査が進められている人が「退去強制令書が発付される前の人」で、審査が終わって国外退去が決定された人が「退去強制令書が発付された後の人」です。
この違いで許可されるための条件や、許可後にどのような生活ができるのかが変わってきます。
退去強制令書が発付される前の人の場合
「退去強制令書が発付される前の人」とは、退去強制処分の審査が進められている人のことです。
- 見守ってくれる監理人がいること
- 主任審査官が、申請した外国人が逃亡したり証拠を隠滅するおそれや、収容することでの健康状態に与える影響や家族関係に与える影響などを総合的に考慮して、収容しないで退去強制手続を行うことを相当と認めること
※監理人についての詳細はこちらをご確認ください。
監理措置が認められた場合には、その人には住居が指定され行動できる範囲も制限されます。
また入管からの呼出しに対応して入管へ行く義務も付けられます。
その他には、逃亡したり証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件が付されます(法第44条の2第1項又は第6項)。
そしてその人の逃亡などを防止するために主任審査官が必要と認める場合は、300万円を超えない範囲内で保証金を納付することが条件としてつけられることがあります(法第44条の2第2項又は第6項)。
もしも監理措置の条件に違反して、逃亡したり正当な理由なく呼出しに応じない人には、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています。
また、交付される監理措置決定通知書には、携帯・提示する義務があり、この義務に違反した場合は、10万円以下の罰金に処する旨規定されています(法第72条又は法第76条)。
監理措置が許可された日か直近に届出をした日から3ヵ月を超えない範囲の入管から指定された日に、担当の地方出入国在留管理官署の主任審査官に対して、監理措置の条件の遵守状況や報酬を受ける活動の許可(仕事の許可のこと)で仕事の状況等を届け出る必要があります(法第44条の6)。
この届出は郵送ではできません。本人が管轄の入管の窓口で届出書を提出してください。
在留資格がない場合は、原則として働くことが認められていません。ただし退去強制処分の審査中の人が生活のために必要だと認められるときは、申請すれば、生活維持に必要だと考えられる範囲内で、働くところを指定するような条件で、例外的に就労を認められることがあります(法第44条の5第1項)。
この手続きには下記のような書類の提出が必要です。郵送では受け付けてもらえないので、管轄の入管へ持参して申請します。
なお就労可能な在留資格を持っている場合に、その在留資格に応じた仕事を行うのであれば許可の申請を行う必要はありません。
- 報酬を受ける活動の許可申請書
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
- 就業予定機関について、本店又は事業所等が本邦内にあることを疎明する資料(パンフレット、登記事項証明書など)
- 就業予定機関の直近3月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印があるものに限る。)又は給与所得支払事務所等の開設届出書の写し
- 被監理者の収入又は資産を疎明する資料
- 被監理者と生計を一にする親族等の収入又は資産を疎明する資料
- 監理人その他の者からの援助の有無及びその額を疎明する資料
- 住居の賃貸借契約書の写し(賃貸借契約を締結している場合)
- その他参考となる資料
退去強制令書が発付された後の人の場合
退去強制令書が発付された後の人とは、審査で国外への退去処分(退去強制)がすでに決定している人の事です。
- 見守ってくれる監理人がいること
- 主任審査官が、申請した外国人が逃亡したり証拠を隠滅するおそれや、収容することでの健康状態に与える影響や家族関係に与える影響などを総合的に考慮して、国外への送還のときまで収容しないことが相当と認めること
※監理人についての詳細はこちらをご確認ください。
退去強制令書が発付された人が働くことはできません。
もしも収入を伴う仕事をした場合は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する旨が定められています。
監理措置が認められた場合には、その人には住居が指定され行動できる範囲も制限されます。
また入管からの呼出しに対応して入管へ行く義務も付けられます。
その他には逃亡や不法就労を防止するために必要と考えられる条件も付けられます。
そしてその人の逃亡などを防止するために主任審査官が必要と認める場合は、300万円を超えない範囲内で保証金を納付することが条件としてつけられることがあります。
もしも監理措置の条件に違反して、逃亡したり正当な理由なく呼出しに応じない人には、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています。
また、交付される監理措置決定通知書には、携帯・提示する義務があり、この義務に違反した場合は、10万円以下の罰金に処する旨規定されています(法第72条又は法第76条)。
監理措置が許可された日か直近に届出をした日から3ヵ月を超えない範囲の入管から指定された日に、担当の地方出入国在留管理官署の主任審査官に対して、監理措置条件の遵守状況等を届け出なければなりません(法第52条の5)。
この届出は郵送ではできません。本人が管轄の入管の窓口で届出書を提出してください。
監理措置決定を受けた人には、監理措置決定通知書が交付されます。
なお、在留カードを持っている場合を除いて、監理措置決定通知書を常に携帯しなければなりません。また権限ある官憲に要求されたときは、監理措置決定通知書を提示しなければなりません。
指定される行動範囲は指定住居の都道府県の区域内に制限されます。ただし未成年者又は高等学校等に在学している人で、通学状況が明らかにわかる場合には、行動範囲が制限されないこともあります。
監理人とは
監理措置制度のキーポイントは「監理人による対象者の適切な見守り」です。このことによって対象者が施設に収容されることなく社会で一定の条件で生活できるようになります。
監理人になるために特別な親族関係や法律資格などは必要ありませんが、要件としては下記のようなことが求められます。
- 監理人の責務を理解している人
- 監理措置の決定を受けようとする人の監理人となることを承諾している人
- 任務遂行の能力を考慮して適当と認められる人
上記の3つの要素を持っている人が対象者の基本で、実際には主任審査官が選定します。
ですのでこの制度の適用を希望する外国人の親族や知人だけではなく、会社の関係者や、支援してくれる人、または弁護士や行政書士などの専門職の人達なども監理人になることができます。
おもに下記の4つが監理人の責務とされています。
※被監理者とは、この制度を利用する外国人の方です。
- 被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと。
- 被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し援助を行うよう努めること。
- 主任審査官から報告を求められたときは、報告を行うこと。
- 次に掲げる事由が発生したときは、届け出るべき事由が発生したときから7日以内に届け出なければならないこと。
おおきく退去強制令書が発付される前の被監理者の監理人の場合か、退去強制令書が発付された後の被監理者の監理人で異なります。
1 次のいずれかにあてはまることを知ったとき。
- 被監理者が逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
- 被監理者が証拠を隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
- 被監理者が監理措置条件に違反したとき。
- 被監理者が法第19条第1項の規定に違反する活動を行ったとき(在留資格外の仕事をした場合)、法第44条の5第1項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動(在留資格をもって在留する者による活動を除く。)をしたとき、または収入を伴う事業を運営する活動を行ったとき。
- 被監理者が第44条の6の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 被監理者が死亡したことを知ったとき。
3 次のいずれかに該当する事由が発生したとき。
- 監理人の氏名や法人名、電話番号なその連絡手段となる情報を変更したとき。
- 監理人と被監理者との間に親族関係(婚姻の届出をしていない内縁関係も含む。)が終了したとき。
- 監理人と被監理者との間に雇用関係がある場合において、その雇用関係が終了したとき。
- そのほか、監理人又は被監理者に関する事項について、主任審査官が監理措置を継続することに支障が生ずるものとして届出を求めることとしたとき。
1 次のいずれかに該当することを知ったとき。
- 被監理者が逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
- 被監理者が収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行い、又はこれらの活動を行うと疑うに足りる相当の理由があるとき。被監理者が監理措置の条件に違反したとき。
- 第52条の5の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 被監理者が死亡したことを知ったとき。
3 次のいずれかに該当する事由が発生したとき。
- 監理人の氏名や法人名など、電話番号その他の連絡手段となり得る情報を変更したとき。
- 監理人と被監理者との間に親族関係(内縁関係を含む。)が終了したとき。
- 監理人と被監理者との間に雇用関係がある場合において、その雇用関係が終了したとき。
- そのほか、監理人又は被監理者に関する事項について、主任審査官が監理措置を継続することに支障が生ずるものとして届出を求めることとしたとき。
主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になったときや、監理人に任務を継続させることが相当でないときは、監理人の選定を取り消すことができます。
監理人を辞任する場合は、辞任しようとする日の30日前までに、主任審査官に届け出るように努めなければなりません。
監理措置の取り消し
下記にあてはまるような場合に、監理措置が決定されても取り消されることがあります。
- 被監理者が納付期限までに保証金を納付しなかったとき。
- 監理人が取り消されたり、死亡した場合などで、新たに監理人になる人がいないとき。
この他には下記のようなことも取り消しの理由になります
- 被監理者が逃亡したときや逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
- 被監理者が監理措置の条件に違反したとき。
- 被監理者が主任審査官に対して必要な届出をしなかったときや虚偽の届出をしたとき。
- 被監理者が不法就労活動をしたとき(報酬を受ける活動の許可を受けずに働いた場合も含む。)。

初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください。