高度専門職ビザに該当する人の特徴と、申請前に確認すべきポイント
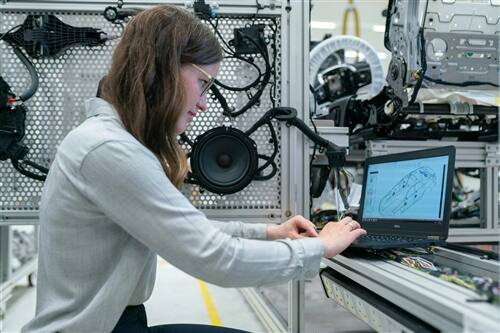
高度専門職ビザは、単に「70点あるかどうか」だけで決まる制度ではありません。
実務では、学歴・職歴と実際の職務内容の整合、年収の裏付け資料、会社側の説明内容などが審査結果を左右します。ポイントが70点に到達していても、根拠資料の整理や説明の組み立てによっては不許可となることがあります。
まずは、ご自身がどの区分(イ・ロ・ハ)に該当するのか、そしてポイントをどこまで資料で裏付けられるかを確認することが重要です。
加えて、「70点はあるのに不許可が不安」「転職予定がある」「永住短縮を狙ってよいか」など、判断が分かれやすい点を“チェック項目”として整理します。
| 高度専門職ビザの概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Highly Skilled Professional |
| 種類 | 高度専門職1号 |
| 高度専門職2号 | |
| 在留期間 | 高度専門職1号:5年 |
| 高度専門職2号:無期限 | |
| 条件 | ポイントの合計が70点以上など |
| 優遇内容 | 副業が可能、永住者申請の条件が緩和される、など |
高度専門職で利用できる優遇措置(在留・家族帯同など)
高度専門職ビザでは、在留や家族帯同に関する優遇が利用できます。主なポイントは次のとおりです。
高度専門職「イ・ロ・ハ」の種類
高度専門職1号は、職種によって次の3つの種類に分かれます。
申請の組み立て(仕事内容の説明、根拠資料の出し方)が変わるため、最初に種類の整理が重要です。
- イ:高度学術研究活動(大学・研究機関等での研究/研究指導など)
- ロ:高度専門・技術活動(理系・文系の専門性を活かす業務。実務では「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務が多いです)
- ハ:高度経営・管理活動(経営・管理に相当する活動)
さらに、高度専門職2号は、高度専門職1号で一定期間働いた人が対象になり、在留期間や活動の制限が大幅に緩和され、永住に近い安定した在留が可能になります。
ポイント制による認定の仕組み
ただし、実務では「点数が足りるか」だけでなく、その点数を“資料で説明できるか”が重要です。
- 学歴:学位の種類、卒業証明、専攻の説明
- 職歴:在職証明、職務内容、期間の裏付け
- 年収:雇用条件書、給与額の説明、課税資料など
- 研究実績・資格等:該当する場合のみ、根拠資料で明確に
- Aさんは、現在28歳です
- 日本の大学に留学して卒業しています。
- 大学在学中には日本語能力試験N1に合格しました。
- 大学を卒業してからは日本企業で4年以上働いています。
- 年収は約550万円です。
- 現在のビザは技術・人文知識・国際業務ビザです。
|
項目 |
評価される点 |
ポイント |
|---|---|---|
|
学歴 |
大学卒業 |
10 |
|
実務経験 |
3年以上の実務経験 |
5 |
|
年収 |
550万円 |
15 |
|
年齢 |
現在28歳 |
15 |
|
ボーナスポイント1 |
日本の大学を卒業している |
10 |
|
ボーナスポイント2 |
日本語能力試験N1合格 |
15 |
|
獲得ポイント 合計 |
70 |
|
実際に申請する際には、このポイントだけでなく、高度専門職1号の具体的な条件を確認することが重要です。
高度専門職ビザで判断に迷いやすいケース
高度専門職ビザは、ポイントが70点に届くかどうかが気になる制度ですが、実際には「どのような目的で申請するのか」「現在の状況がどうか」によって、考え方が変わります。
ここでは、判断に迷いやすい代表的なケースを整理します。
70点ちょうどで申請するケース
日本の大学卒業+日本語能力試験N1+一定年収などで70点ちょうどに到達するケースです。
この場合、ポイント計算自体は成立していても、
- 職歴証明に具体性がない
- 年収の説明資料が弱い
- 現在の業務と学歴専攻の関連が薄い
といった理由で不許可になることがあります。
70点ギリギリの場合は、単に点数を示すだけでなく、「なぜその人材が高度専門職に該当するのか」を資料全体で説明することが重要です。
永住者申請までの期間を短縮するために高度専門職へ変更するケース
高度専門職ビザは、80点以上の場合に1年で永住申請が可能となる優遇策があるので、永住者の申請に必要な期間を短縮する目的で選択されることがあります。
ただし、永住を見据える場合は、
- 直近の納税状況
- 社会保険料の支払い状況
- 転職予定の有無
なども含めて慎重に検討する必要があります。
単にポイントが高いという理由だけで選択すると、将来の永住申請時に不利になる場合もあります。
転職予定があるケース
高度専門職ビザは、在留中の活動内容との整合が重要です。
特に高度専門職1号では、許可時に勤務先が指定されるため、申請直後に転職予定がある場合や、業務内容が大きく変わる予定がある場合は、慎重な検討が必要です。
高度専門職ビザは「ポイントが足りるかどうか」だけではなく、そのポイントをどのように裏付け、どの目的で申請するのかが重要になります。制度理解と実務整理の両方が必要な在留資格といえます。
「70点/80点に届くか」「根拠資料の出し方が不安」など、まずは状況を簡単に教えてください。
行政書士が内容を確認し、必要資料の整理方針をご案内します。
※3項目だけで簡単に送れます
審査でのポイント
前章では、判断に迷いやすいケースを整理しました。
ここでは、実際の審査で重視される視点を整理します。
- 学歴・職歴と、実際の職務内容の関連性
- 雇用条件(年収・職位・業務内容)の明確さ
- ポイント計算の根拠資料が十分か(読み手が再計算できる状態か)
- 提出資料に矛盾や欠落がないか
- 勤務先(受入れ機関)の説明が足りているか
不許可になりやすいケースと、事前にできる対策
1 ポイントは70点以上だが、根拠資料が弱い
例:職歴の証明が「在職していた」だけで、実務内容が分からない/学位や専攻が読み取れない
対策:資料から内容が一読で分かる形に並べ替え、説明文(理由書等)で補います。
2 学歴・職歴と職務内容のつながりが弱い
例:専攻と業務が離れて見える/職務内容が抽象的
対策:職務内容を具体化し、どの知識・経験をどう使うのかを職務説明・理由書で一致させます。
3 年収や雇用条件の説明があいまい
例:給与の内訳が不明確/契約書と説明がズレている
対策:雇用契約書・内定通知・給与規程など、金額と条件が一致する資料で固めます。
4 会社側資料が薄く、受入れの合理性が伝わらない
例:事業内容・組織・採用理由の説明が弱い
対策:会社概要、事業内容、業務の必要性、体制の説明を整えます。
5 提出資料に矛盾や抜けがある
例:履歴書と職歴証明が一致しない/翻訳の表記ゆれ
対策:提出前に、「日付・名称・金額・役職・期間」の整合チェックを行います。
「点は足りるのに不許可が不安」な方へ
不許可は、職務内容の説明・学歴職歴との整合・資料の矛盾/欠落で起きやすいです。
申請前に、提出資料の整合チェック(役職・期間・金額・表記ゆれ)と、説明文の作り方を整理します。
→ 無料相談はこちら(メール)
(原則、翌営業日までにご返信)
TEL:03-6697-1681(平日9時〜18時)
申請に必要な書類(主に高度専門職1号ロ)
この章では、申請件数が多い「高度専門職1号(ロ:高度専門・技術活動)」に絞って、必要書類を整理します。
イ(高度学術研究)・ハ(高度経営・管理)は、活動内容により求められる資料のポイントが異なるため、本ページでは共通部分+ロの資料整理を中心に解説します。
※イ・ハでの申請を予定している方は、前章までの考え方(区分整理・根拠資料の裏付け)を踏まえた上で、個別事情に応じて追加資料が必要になります。
以下では「高度専門職1号(ロ)」の申請を前提に、新規(COE)・変更(国内)・2号への変更の3パターンに分けて、基本書類を整理します。
新規に高度専門職1号ビザを申請する(これから来日する場合)
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(会社のカテゴリーに応じた書類を提出)
5 ポイント計算表
6 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上になることを証明できる資料を提出します。該当するポイント項目の全ての資料を提出する必要はありません。)
他のビザから高度専門職1号ビザへ在留資格を変更する場合
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 パスポートと在留カード (申請時に提示します。)
4 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(会社のカテゴリーに応じた書類を提出)
5 ポイント計算表
6 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上になることを証明できる資料を提出します。該当するポイント項目の全ての資料を提出する必要はありません。)
7 手数料納付書(変更が許可された後に使用します。収入印紙で変更手数料を納付します。)
高度専門職2号に変更する場合
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 パスポートと在留カード (申請時に提示します。)
4 勤務先がどのカテゴリーに属しているかが分かる書類(提出資料がカテゴリーによって分かれている場合に提出します。)
5 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(勤務先がカテゴリー1か2の場合は不要です。)
6 直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する下記の資料
1 住民税の納付状況を証明する下記の資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
住所のある市区町村の役所や役場で入手できます。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つを提出します。市区町村で直近5年分の証明書が発行されない場合には、発行できる最長期間分を提出します。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書など)
直近の5年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その期間の分を提出します。
2 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書
住所を管轄する税務署で入手できます。納税証明書は証明を受けようとする税金を証明日現在で払っていないものがないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。上記の税目全てについての納税証明書を提出します。
3 次のいずれかで所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記の書類などに準ずるもの 適宜
7 申請人の「公的年金」と「公的医療保険の保険料」の納付状況を証明する下記の資料
過去2年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度で、下記で該当する資料を提出します。(複数の公的年金制度と公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)基礎年金番号や医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類を提出する場合には、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号が分からないように黒塗りするなどして提出します。
直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウで、アとイの資料か、ウの資料を提出します。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
封書で「ねんきん定期便」が送付されている人(35,45,59歳)は、同封されている書類のうち〈目次〉で、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』に記載された全ての書類を提出します。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
直近2年間に、国民年金の被保険者になったことがある人は、「各月の年金記録」の中にある「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も提出します。
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近2年間で国民年金に加入していた人は、その加入期間分の領収証書(コピー)を全て提出します。領収書などが見つからない人は、その理由を書いた理由書を提出する必要があります。また直近の2年間をすべて国民年金に加入していた人は、その直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できるのであれば、上記ア又はイの資料を提出する必要はありません。
直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する下記の資料
ア 国民健康保険被保険者証(コピー)
国民健康保険に加入している人が提出します。
イ 健康保険被保険者証(コピー)
健康保険に加入している人が提出します。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間の分を提出します。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間の分の領収証書(コピー)を全て提出します。領収書がみつからないなどの場合は、その理由を書いた理由書を提出します。
申請する人が「社会保険適用事業所の事業主」の場合
社会保険適用事業所の事業主の人は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間でその事業所で事業主であった期間の「事業所の公的年金と公的医療保険の保険料に関する資料」として下記のアとイのいずれかを提出します。
健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証書(コピー)の提出ができない場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(コピー)
申請する人(事業主)が保管している直近2年間で事業主でいた期間の、全ての期間の領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記のイを提出します。
イ 社会保険料納入証明書か、社会保険料納入確認(申請)書(どちらも未納の有無を証明・確認する場合)
8 ポイント計算表(行おうとする活動に応じた分野のものを提出します。)
9 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出します。ポイント項目すべてに関係する資料を提出する必要はありません。)
10 手数料納付書(ビザの変更が許可された場合に、変更の手数料を収入印紙で納付します。)
高度専門職2号ビザに関する必要書類は、年金、社会保険、税金など支払い状況に関する公的記録など「永住者」の申請書類に似てとても複雑です。
書類準備や申請手続きについてご質問やご相談はお気軽に当事務所へご連絡ください。
高度専門職ビザのよくある質問|ポイント計算・必要書類・不許可リスク
本ページでは、高度専門職ビザ(高度人材ポイント制)の仕組み、優遇措置、ポイント計算、そして不許可になりやすいポイントまで整理しました。
最後に、実務で質問の多い点をFAQ形式でまとめます。申請の準備や社内検討のチェックにお役立てください。
学歴・職歴・年収などをポイントで評価し、一定の点数(目安:70点以上)を満たした方が申請できる在留資格です。認められると、在留期間の優遇や永住申請までの期間短縮などの優遇措置を受けられます。
高度専門職1号はポイント制で認定される在留資格で、主に5年の在留期間などの優遇があります。高度専門職2号は1号で一定期間活動した方が対象で、在留期間や活動の制限が大幅に緩和され、永住に近い安定した在留が可能になります。
高度専門職1号は、行う活動の種類によって「イ(高度学術研究活動)」「ロ(高度専門・技術活動)」「ハ(高度経営・管理活動)」に区分されます。どの区分で申請するかにより、仕事内容の整理や提出資料の作り方が変わります。
70点は申請の入口の目安であり、許可を保証するものではありません。ポイントの根拠資料が不足していたり、学歴・職歴と職務内容の関連性が弱かったり、書類の整合が取れていない場合は不許可となることがあります。
ポイント計算の根拠資料が不十分、学歴や職歴と職務内容の関連性が弱い、年収や雇用条件の説明不足、会社の事業実体や安定性の説明不足、提出資料に矛盾や欠落がある場合などが典型例です。
合計点を裏付けるために、加点を主張する項目については原則として根拠資料を用意します。提出する資料の種類や分量は申請人の状況により異なるため、職歴・学歴・年収・研究実績などの主張に合わせて整理することが重要です。
在留資格認定証明書(COE)交付申請書または在留資格変更許可申請書、写真、ポイント計算表、学歴・職歴・年収などを証明する資料、勤務先・事業内容に関する資料などが基本です。申請区分や勤務先のカテゴリー、個別事情により追加資料が必要になることがあります。
高度専門職ビザで3年以上活動していること、または、高度人材ポイント制で80点以上の場合は、1年以上活動していることが条件となります。
70点ギリギリで根拠資料の整理が難しい場合、職務内容と学歴・職歴の関連性の説明が必要な場合、会社資料や雇用条件の説明を丁寧に作る必要がある場合などは、事前に専門家へ相談することで不許可リスクを下げやすくなります。
高度専門職ビザは「ポイントが足りるか」だけでなく、そのポイントを根拠資料でどう説明するか、そして学歴・職歴と職務内容の整合が結果を左右しやすい手続きです。
「70点はあるが資料の出し方に不安がある」「会社側の説明をどう整えればいいか分からない」など、個別事情が絡む場合は、当事務所までお気軽にご相談ください(初回ご相談は無料です)。
外国人の就労に関する在留資格について、ご相談ください。
行政書士が直接対応いたします。
実際の手続きでは「現在の状況」「これから行う業務内容」により判断が分かれることがあります。
事前にご相談いただくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。
※3項目だけで簡単に送れます
お電話での相談はこちら
TEL:03-6697-1681(平日9時〜18時)

